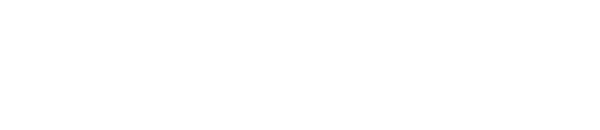みなさん、こんにちは
総合子ども学科コモンルームです
だいぶ秋らしくなってきた今日この頃
みなさん、いかがお過ごしですか
今回は、コモンルームで行われた山下先生の2ゼミ(「総合子ども学基礎演習ⅡB」の様子をお伝え致します
山下ゼミでは、子育て支援をテーマに、妊娠期からの支援、障がい児の子育て支援、障がい者の子育てへの支援、地域の子育て支援活動、子育て家庭とのコミュニケーションツールなど、これまでの学びで触れることの少なかった内容を学習したり、体験しようとしています。
少子化が進むなかで、子育てに不安を抱えていたり、孤立したり、子どもに不適切な関わりをしてしまう子育て家庭が多く存在します。妊娠、出産、保育、と切れ目のない支援が求められて、公的な取り組みも進められています。“子ども”を学ぶ私たちも、まずは妊娠期からの課題や支援を考えるために、この日、一時的に“妊婦さん”になってみました。
看護学科から妊婦ジャケットをお借りして、妊婦疑似体験に挑戦です。15名の学生が4つのグループに分かれて、一人ずつ体験したのですが、7kgものジャケットの重みにみんなビックリ!安全に体験するため腰にベルトを巻き、グループメンバーがサポートしながら、椅子に座ったり立ったり、階段を昇り降りし、靴紐を結んでみたり、トイレも!コモンルームには抱っこやオムツ替えを学習するために赤ちゃん人形が何人もいるのですが、その子たちを抱っこしてみたり・・・
立ったり座ったり、機敏には動けない。
しゃがんだり、前かがみになるのが難しい。
足元が見えづらく、階段の昇り降りが不安で危ない。
自然に背中が反って、足も開いて歩くようになる。
家事が大変そう。重い荷物を持ったり、上の子を抱っこしたりも負担になるな。
しかし、
少しずつ大きくなるお腹を見ると、とても愛おしく感じられるだろうなあ。
子どもが生まれるのを心待ちにするだろう。
重いけど、その重みで幸せを感じるだろうし、嬉しいだろう。
大きなお腹で仕事もしている人もいて、妊婦さんはすごい!
自分の体調だけでなく、お腹の子どものことも考えて、責任をもって行動しないといけないな。
など、体験後にさまざまな感想が出されました。
体験中に「切れ目ない支援」についても資料をもとに学んだのですが、公的な支援だけでなく、いま、私たちにできることも考えてみました。
バスや電車では席を譲る。
声かけして、荷物を持ったり、ベビーカーをたたんだり持ったりを手伝う。
ぶつかったりしないように周囲にも気を配り、階段では手を貸したりする。
妊婦さんや周りの人に、子育て支援サービスの情報などを伝える。
これからは、子どもだけではなく、妊婦さんやお母さんへの眼差しがさらに優しくなりそうです
看護学科の川村先生、池内先生、ありがとうございました
CLOSE