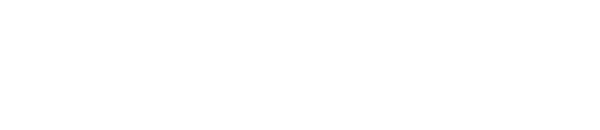こんにちは
湿気が多く、なんだかスッキリしませんね
体調を崩しやすいため、みなさん気をつけてくださいね
今回は、山下先生の『家庭支援論』の授業で、ゲストスピーカーをお呼びして講義して頂いたときのお話です
--------------------------------------------------
総合子ども学科では「家庭支援論」の授業で、保育所や認定こども園などにおける家庭支援、保護者支援を学んでいます。保護者の方々とのコミュニケーションはとてもたいせつですが、外国にルーツをもつ子どもたち、保護者の方々が増えて、保育現場では日常のコミュニケーションが難しい場面があるようです。
そこで、家庭支援の実際として、日本語に不慣れな保護者への支援の実践を学び、多様な文化を理解することを目的に、社会福祉法人 大阪ボランティア協会から柳瀨 真佐子先生と瀧本 宏子先生を講師としてお招きして、「日本語でつたえるコツ」ワークショップを行いました。
瀧本先生は保育士として公立保育所で勤務されたのち、現在は民間保育所の園長先生をされています。長年の保育現場でさまざまな国から日本に来た保護者と接してこられ、コミュニケーションがうまくとれなくて失敗したこと、文化の違いによる誤解、何度も工夫をしたことをユーモアを交えてわかりやすくお話くださいました。
「できないことはない」・・・二重否定
「おこしください」・・・・・敬語
「ほんで、」・・・・・・・・方言
お弁当についても、お弁当そのものの文化がない国、おかずに生ものなどを入れる保護者(日本は湿度が高く、食中毒の危険から、お弁当のおかずはすべて火を通します)、何度も繰り返し説明をしたり、現物を見せたり、試行錯誤を重ねてこられたようです。
学生は、保育所などでよく使われる言葉を“やさしい日本語”に変換する練習問題に挑戦しましたが、“やさしい日本語”はやさしくない!ようで、みんな苦戦していました。「遠足のお知らせ」例文も、私たちはあたりまえに目にしてきましたが、日本語に不慣れな人が読むと、わかりづらい文章なのだということがよくわかりました。
柳瀨先生からは、日本語でつたえるコツとして、35のルールを教えていただきました。日本語に不慣れな保護者の方々だけではなく、コミュニケーションツールとして広く応用が利くように思いました。お二人が活動されている「日本語でつたえるコツ」広げる委員会では、“コツ”を記した冊子を作られていて、ホームページからダウンロードできるそうです。海外に行って、現地で困ったときに頼れる機関の一覧も掲載されているようですので、検索してみるといいですね。
受講した4回生のなかには、来年度には小学校や幼稚園の教諭、認定こども園の保育教諭、保育所保育士として、外国人の保護者の方々との実際に接することもあるでしょう。今回のお話はすぐにでも実践に活かせますね。
柳瀨 真佐子先生、瀧本 宏子先生、ありがとうございました。
CLOSE