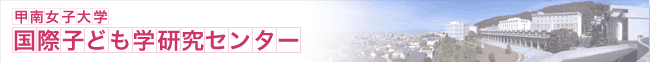
|
HOME > 「子ども学」講演会 > 2017年度 > 主催する「子ども学」講演会をご紹介します。 2017年度第116回「子ども学」講演会 2017年12月7日子どもは未来子ども学という名前は、社会的に認知されてきていますが、まだその意義や課題についての理解は十分ではないと思います。小児科医として子どもの身体から始まり、子どもの発達とその障害、世界の子どもを巡る貧困や権利など、子ども学の課題はたくさんあります。皆さんと子ども学の意義と、子どもの明るい未来に向けた課題について考えてみたいと思います。
第115回「子ども学」講演会 2017年11月2日誕生のインファンティア~子どもはどんな不思議を体験しているのか~子どもの頃、誕生について何か不思議を感じたことはありませんか。赤ちゃんはどこから来ると思っていましたか。死んだらどうなるの?と思ったことはありませんか。「生まれる前、僕はどこにいたの」と尋ねた少年のこと、「子どもの頃、母親に『僕は今どうして生きているの?』と責めて困らせたことがありました。」と書いた学生のことなどもお話ししたいと思います。
第114回「子ども学」講演会 2017年10月12日子ども虐待と脳科学~アタッチメント(愛着)の視点から~乳幼児期に家族の愛情に基づく情緒的な絆(アタッチメント)が形成され、 安心感や信頼感の中で興味・関心が拡がります。しかし人生の早期に幼い子どもが想像を超える恐怖と悲しみにさらされる被虐待体験は、子どもの人格形成に深刻な影響を与えてしまいます。子どもたちは深い心の傷(トラウマ)を抱えたまま、人生に立ち向かわなければならないのです。被虐待児たちが受けるトラウマは「後遺症」となり、将来に渡って子どもに影響を与えるのです。
第113回「子ども学」講演会 2017年7月13日女の子の育て方いまどきの女の子で、男が女よりエライ!と思ってるカン違い女子は誰もいません。女も男も能力は同じ、と自然な平等感覚を持っているのに、学校でも社会でも、女は男より不利な扱いを受けます。なぜ?どうして変わらないの?どうすればいいの?女の子はどう育てたらいいの?これからの時代を、女はどうやって生き抜いていったらいいの?…それをご一緒に考えてみましょう。
第112回「子ども学」講演会 2017年6月22日保育教諭の時代乳幼児教育・保育の現場は、多くが認定こども園に移行しつつあります。まもなく「幼保連携型認定こども園教育・保育要領」が告示され、平成30年4月より施行されます。認定こども園の先生は、保育士でなく、幼稚園教諭でもなく、正式な名称として、「保育教諭」と呼ばれます。しかし、保育教諭という資格はありません。「保育教諭」とは何なのか?求められる資質について考えます。
第111回「子ども学」講演会 2017年5月18日子育ち子育てエンパワメント~コホート研究から~エンパワメントとは、人びとに夢や希望を与え、勇気づけ、人が本来持っているすばらしい、生きる力を湧き出させることです。ちょうど清水が泉からこんこんと湧き出るように、一人ひとりに潜んでいる活力や可能性を湧き出させます。子育ち子育てエンパワメントは、子どもにかかわる人びとの大切な役割です。その根拠をコホート研究から明らかにします。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Copyright (c) International Center for Child Studies (Konan Women's University),
All rights reserved.
このサイトに掲載する文章、イラスト、画像等の無断転載を禁じます。