 雨が降ると、陸から海に養分が流れる
雨が降ると、陸から海に養分が流れる
この日は雨が降っていました。
学生は、景色のいい海なので、晴れていたらよかったのに、と言いました。
すると、養殖場の経営者からは、こんな返事がかえってきました。
「雨、降っとるやろ?
僕らは、いつも貝のことしか考えてへんから、
雨降ると、何を思うかいうと、
餌(えさ)が来る、餌が来る。
お母さんがおっぱいあげるみたいな感じで、
雨降って陸の落ち葉のところから水が流れて、
海に行って養分になる。
そしたら、海の中で植物性プランクトンが増えて、
それをアコヤ貝が喜んでパクパクパクパク食べる。
この英虞湾(あごわん)は、基本がエメラルド・グリーン。
ブルーじゃなしにグリーン。
何でかいうたら、植物性プランクトンだから、
植物性プランクトンが居るからね。
だから、真珠の養殖をしていると、この雨が嬉しい」
 アコヤ真珠ができるまで
アコヤ真珠ができるまで
(1)1年目の春、
アコヤ貝の稚貝(ちがい=赤ちゃん貝)を購入して網に入れ、
筏(いかだ)から海中に吊す。
(2)冬になると、
南のほうの水温の高い海に、網ごと車で運び、
そこの筏で海中に吊す。
(3)2年目の春、こちらの海に戻す。
(4)2年目の冬、また南の海に運ぶ。
この時は、網から籠(カゴ)に移して、ぎゅうぎゅう詰めにする。
そうすると、冬の間にアコヤ貝が少しだけ弱る。(「抑制」という作業)
(5)3年目の春、
カゴの中で少し弱ったアコヤ貝をこちらの海に戻して、
貝の身のなかに、「核」を埋め込む。
この核の周りに真珠層が巻かれていく。
*元気なアコヤ貝に「核」を埋め込んでも、
異物として出してしまうので、少しだけ弱らせる。
そのかげんが、とても、むずかしい。
(6)3年目の冬。アコヤ貝から真珠を取り出す。
この間ずっと、1週間に1回は、
貝の外に付く牡蛎(かき)やゴミなどを落とす作業が続きます。
台風や津波が来ると、筏が壊れることもあるそうです。
百年前に、湖のような静かな英虞湾で始まった真珠の養殖は、
現在も、たいへんな労力をかけて行われていました。
 お昼にいただいたごちそう
お昼にいただいたごちそう
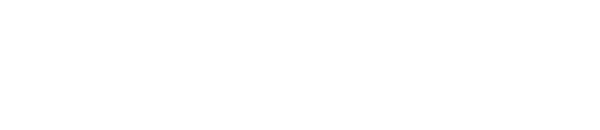




 静かなところ
静かなところ
 雨が降ると、陸から海に養分が流れる
雨が降ると、陸から海に養分が流れる アコヤ真珠ができるまで
アコヤ真珠ができるまで