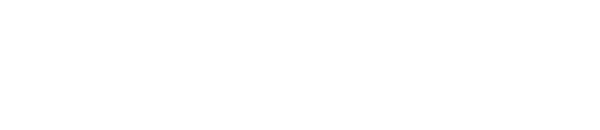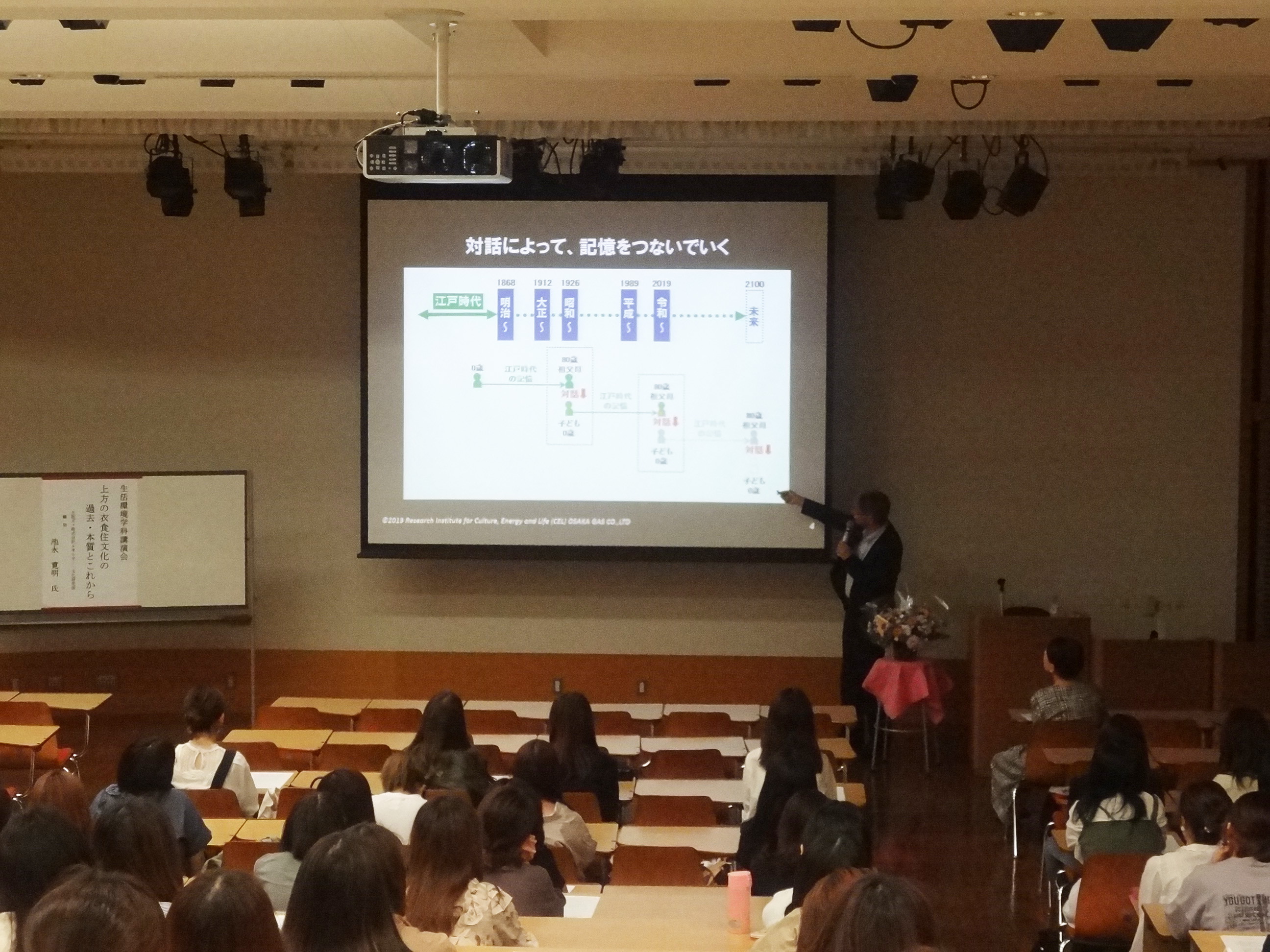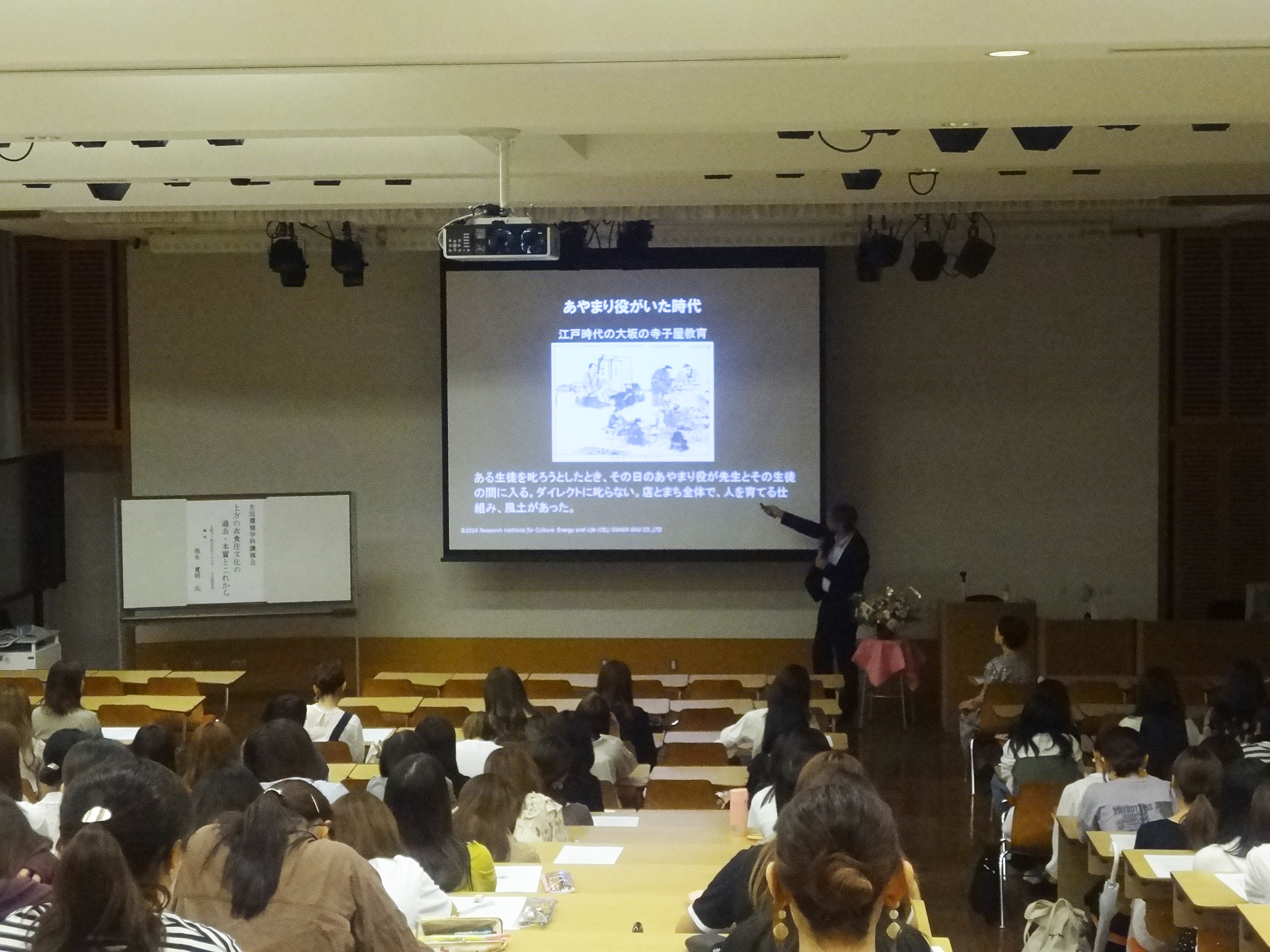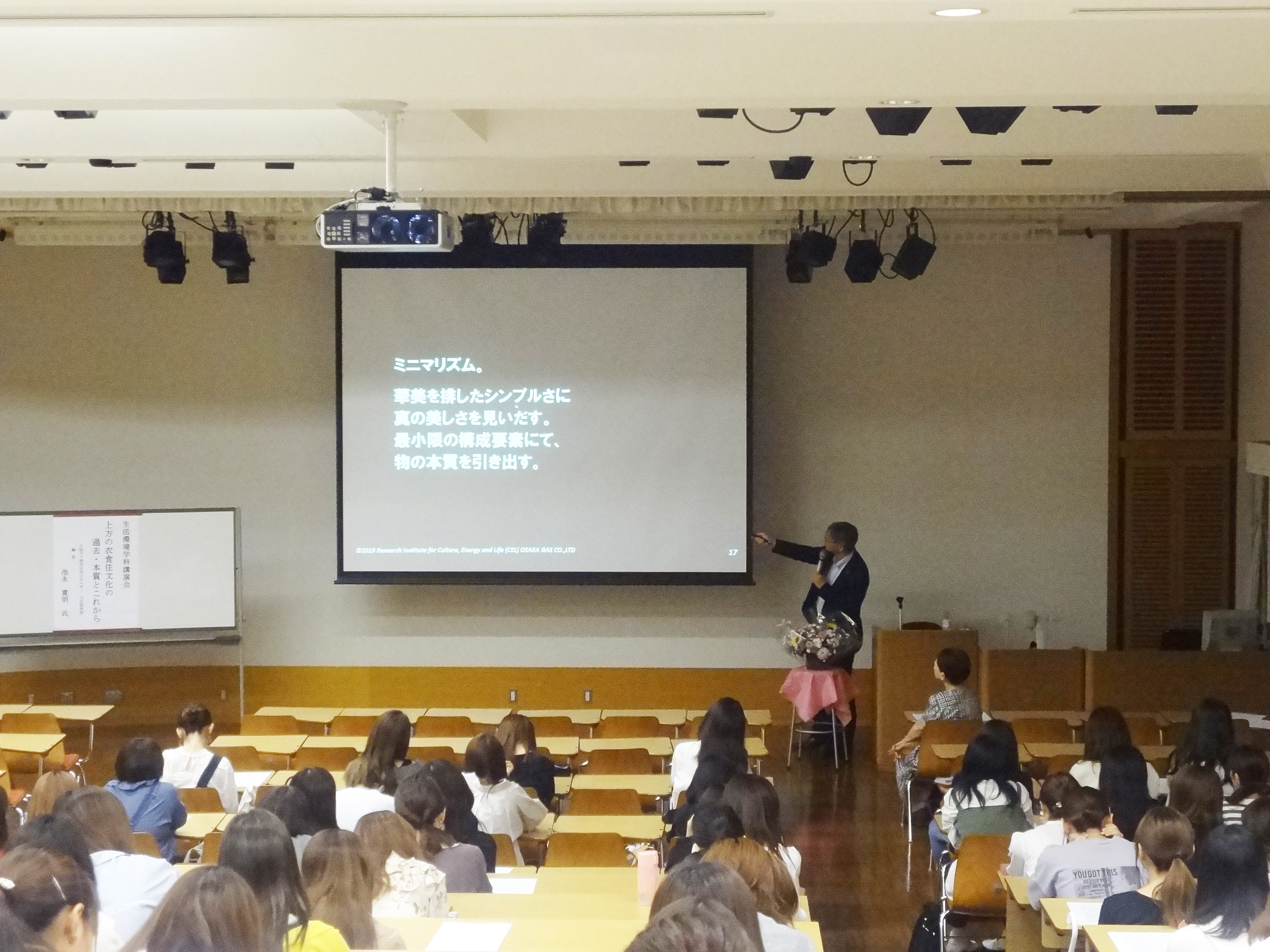こんにちは
本日は10月2日に行われた
講演会の様子をご紹介します
今回は大阪ガスのエネルギー・文化研究所の顧問で
いらっしゃいます池永寛明氏をお迎えし、
「上方の衣食住文化の過去・本質とこれから」を
テーマにお話を伺いました
上方から失われていく言葉の中に、
“なんで、あんたみたいな賢い子がこんなあほなことしたん?”と
いうような言い方があります。
ストレートにきついことは言わない
上方の文化がそこにあります。
これは貿易の都市、大阪・神戸ゆえの文化と言えます。
江戸時代、大阪の寺子屋には「あやまり役」がいて、
何かあればその日のあやまり役が謝り、
その子をダイレクトには叱らない、
町全体で人を育てる風土があったそうです。
しかし、現代ではプライバシーなどが重視され、
昔は根掘り葉掘り話せたことでも
聞き出せなくなり、
周りの人たちの事がよく分からなくなりました。
これらは昔が正しく、
現代が間違っているということではありません。
ただ、昔にあった事柄(コンテンツ)の中から、
なぜそうだったのかという背景(コンテクスト)を探り、
現代に活かす本質をつかめることが重要です。
CLOSE