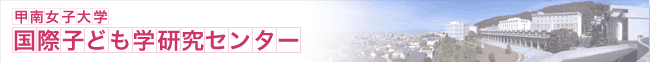
|
HOME > 「子ども学」講演会 > 2002年度 > 主催する「子ども学」講演会をご紹介します。 2002年度第28回「子ども学」講演会 2002年11月14日学校現場における障害児教育学習障害、ADHD(注意欠陥多動性障害)、アスペルガー障害など、学校生活にうまく対応できない子どもたちが、増加してきている。そこで、そのような軽度発達障害の子どもについての理解と対応について、皆で考えてみましょう。 プレゼンター:郷間 英世(奈良教育大学教授) 第27回「子ども学」講演会 2002年10月17日チルドレンズ・ミュージアムミュージアムには、新鮮なヒト、モノ、出来事との出会いがたくさん潜んでいます。ミュージアムからはじまる楽しい学びをみんなで探してみませんか。 プレゼンター:佐藤 優香(国立民族学博物館 非常勤研究員) 第26回「子ども学」講演会 2002年9月26日病院の子どもたち日常生活から切り離され病院での生活を送っている子ども達。自分の病気の心配や、いやな検査・治療にも耐えていかねばなりません。このような子ども達に何が必要なのか皆で考えましょう。 プレゼンター:夏路 瑞穂(中京女子大学人文学部児童学科講師) 第25回「子ども学」講演会 2002年7月11日乳幼児の体操体操とは、一般的には、より早く走るとか、より高く跳ぶ、あるいはより遠くまで投げるための訓練だと考えられている。しかし、3才以下の小さな子どもたちになると、走ること、跳ぶこと、投げること自体がまだできていないのである。それでは、このような小さな子どもたちが、自分のからだを自分の思い通りに動かすことができるようになっていく、いわば身体発達促進のプログラムとはどんなものなのかを、皆で考えてみよう。 プレゼンター:米谷 光弘(西南学院大学教授) 第24回「子ども学」講演会 2002年6月20日音の無い世界で~人工内耳をめぐって~このような題名のアメリカのテレビ番組が、昨年のNHK国際教育番組コンクールでグランプリを受賞した。最新の科学の成果として、一見問題もなさそうなこの「人工内耳」が、どうしてこのような厳しい激論の的になるのか、私たちも考えてみよう。 プレゼンター:一色 伸夫(NHK放送文化研究所・研究主幹) 第23回「子ども学」講演会 2002年6月20日絵本は子どもに何ができるか絵本は古来あらゆる面で、幼い子どもたちの成長の糧となってきました。しかし、絵本というものの魅力ある可能性はまだ開発しつくされたとは言えません。そして子どもたちもまだまだ絵本からいろいろなことを感じ、不思議なことを発見したがっています。
プレゼンター:木曾 秀夫(絵本作家) |
Copyright (c) International Center for Child Studies (Konan Women's University),
All rights reserved.
このサイトに掲載する文章、イラスト、画像等の無断転載を禁じます。