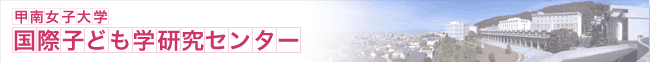
|
HOME > 「子ども学」講演会 > 2004年度 > 主催する「子ども学」講演会をご紹介します。 2004年度第40回「子ども学」講演会 2004年12月9日幼児の話しことばとつくりうた -歌うことの根源を探る幼児がなにげなくつぶやいて歌う「つくりうた」を、でたらめ歌と呼ぶことがあります。 しかし、つくりうたはでたらめではなく、「話しことば」と密接に結びついています。 それではいったい「ことば」と「うた」は何がちがうのでしょうか? 幼児のつくりうたを聞きながら、歌うことの不思議について一緒に考えてみませんか。 プレゼンター:坂井 康子(京都教育大学講師・音声言語研究所研究員) 第39回「子ども学」講演会 2004年11月11日赤ちゃんの行動を科学する赤ちゃんを見ていると自然と"かわいい"という感情が沸き起こってきます。しかし、しっかりと行動を観察すると、驚くほど赤ちゃんの能力があることに気づかされます。赤ちゃんのありのままの姿・行動を、科学的、脳科学的に考えてみましょう。 プレゼンター:小西 行郎(東京女子医科大学乳児行動発達学講座教授) 第38回「子ども学」講演会 2004年9月30日今、不登校に何ができるのか不登校児に対するさまざまなアプローチが行われてきましたが、最近では、その子ども達の中の軽度発達障害児に注目が集まり、特別支援教育が提言されています。ひとつのモデルを示しながら、皆さんと共に考えていきましょう。 プレゼンター:喜田 三津雄(学校法人 喜田学園東林館高等学校理事長) 第37回「子ども学」講演会 2004年7月1日発達加速現象 ~ Acceleration ~日本の子どもは、明治から大正、大正から昭和へと、どんどん成長が早まり、とくに戦後は、世界にその例を見ないほど、成長・成熟を加速させてきた。では、平成の子どもはどうなのか。このような傾向は世界的なのか。また、それは良いことなのか悪いことなのか、考えるべきことは多い。 プレゼンター:日野林 俊彦(大阪大学人間科学部教授) 第36回「こども学」講演会 2004年6月17日心が通う身体的コミュニケーションシステムうなずきや首振りなどの、身体的リズムの引き込みを、ロボットやCGキャラクターのメディアに導入することで、対話者相互の身体性が共有でき、一体感が実感できるコミュニケーション・システムの開発を通して、子ども学研究への応用を皆で考えてみましょう。 プレゼンター:渡辺 富夫(岡山県立大学情報工学部教授) 第35回「子ども学」講演会 2004年5月20日子ども学のすすめ21世紀の科学は、人間を総合的かつ学際的に捉える考え方であり、「子ども学」「赤ちゃん学」もその流れの中から生まれた。いわゆるこれからの子ども観の確立、children's Issues の解決、チャイルドケアデザインなどが、大きな柱となろう。 プレゼンター:小林 登(東京大学名誉教授・甲南女子大学国際子ども学研究センター名誉所長) |
Copyright (c) International Center for Child Studies (Konan Women's University),
All rights reserved.
このサイトに掲載する文章、イラスト、画像等の無断転載を禁じます。