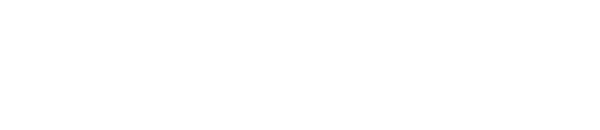インドネシア等、東南アジアからの訪日外国人の増加に伴い、医療機関を受診する人も増えています。看護学科の教育の国際化の一つの柱は医療のグローバリゼーションへの対応能力強化です。そこで、看護リハビリテーション学部と学部間協定を締結しているインドネシアの国立イスラム大学医療保健学部より2名の講師(公衆衛生学科講師Narila Mutia Nasir先生、看護学科講師 Maulina Handayani先生)をお招きし、さる10月14日に「医療と宗教」というテーマで国際セミナーを開催しました。セミナー前に、Nasir先生、Hanadayani先生と看護リハビリテーション学部長秋元典子先生・看護学科長川村千恵子先生と記念撮影をしました(写真右)。
CLOSE