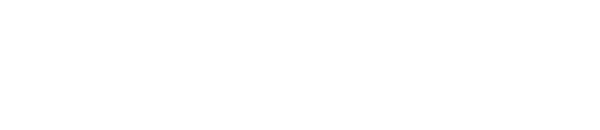こんにちは、多文化コミュニケーション学科です
9月下旬より、後期が始まりました

大学では、サーマルカメラチェックや授業中の換気など、
感染症対策を講じながら、対面式とオンライン授業の併用で授業が行われています
先生方や学生の姿があちこちに見られるキャンパスって、やっぱりいいですね
前期期間中(4月~7月)は大学の外で行う学習を全くできませんでしたが、
後期期間では、しっかり感染予防対策を行いながら、学外でフィールドワークを行う実習も始まりました
野崎先生の3年ゼミでは、前期にテキストなどを通じて学んだ多文化共生の課題を、
大学が立地する東灘区という身近な場で生じている問題として考えるために、
多文化フェスティバル深江でボランティアを行いました
CLOSE