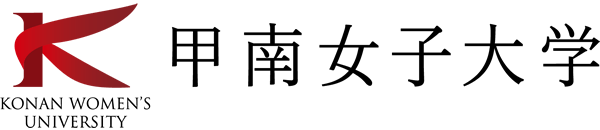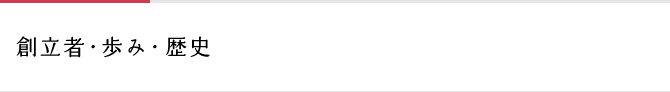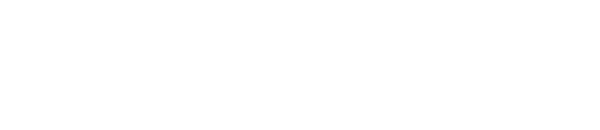学校法人甲南女子学園の創立者である安宅彌吉は、石川県金沢市金石生まれの実業家です。東京高等商業学校(現・一橋大学)卒業、同じ金石生まれの海の豪商と云われた銭屋五兵衛にあこがれ貿易商の道を歩み、戦後の十大総合商社の一角を成した安宅産業を一代で築きました。
また、大阪商業会議所会頭、貴族院議員の要職を務め、激動の明治、大正、昭和にかけて実業界に大きな足跡を残しました。そうした経済人としての活躍にとどまらず、終生の友人として親交の深かった、同郷の宗教哲学者であり世界的な禅思想家の鈴木大拙に対して、研究や出版活動の援助を行いました。郷土である石川県、金沢市の青年たちへの奨学金(安宅育英資金)や神社、仏閣への多額の寄進など、地域貢献にも力を尽くしました。
甲南女子学園の創立にあたっては、新しい時代にふさわしい女子教育のために、官立にない自由な校風の私立の女学校という理想を掲げました。当時官立校は教育方針が画一的であり、多くの定員数が求められていました。豊かな知性と教養を持ち、品格を備えた女性を育てるには、教員と生徒が相互に交流できる少人数でないと、個性を尊重し、自ら創造して学ぶ教育は行えないという考え方をもっていました。
個性を尊重し、自ら創造して学ぶ教育という理念は、今も甲南女子学園に連綿と受け継がています。
甲南女子学園は企業家でありながら教育にも広く力を尽くした安宅彌吉(あたか・やきち)により、1920年(大正9年)に「甲南高等女学校」として創立されました。その後変遷を経て、1964年(昭和39年)に甲南女子大学が開学し、中学校・高等学校・大学・大学院で構成される総合学園に発展し、現在の甲南女子学園の姿に至ります。
甲南高等女学校初代専任校長・表甚六は、校訓「清く 正しく 優しく 強く」を置き、全人教育、特に徳育に主眼を置いて本学の教育精神の基礎を築きました。また当時から私学の独自性を発揮し、官制の画一的教育を排し、「自学創造教育」を行いました。これは本学園の教育方針「全人教育」「個性尊重」「自学創造」として引き継がれています。これらの背景を踏まえ、建学の精神を「まことの人間をつくる」と明文化しました。
甲南女子大学は、創立以来「全人教育」「個性尊重」「自学創造」の教育方針によって、建学の精神の実現につとめ、誠実で品位ある女性を数多く育て、世におくり、社会の信頼と期待にこたえてきました。校訓「清く 正しく 優しく 強く」は、この人間教育の理念をわかりやすく表現したもので、まことの心を養い、人のために尽くし、世界の平和と人類の福祉に貢献するような女性に育ってほしいという願いが込められています。
| 1919年(大正08年) |  当時住吉村に在住した関西財界人たちの手で創立された「財団法人甲南学園私立甲南中学校」の創立委員会席上において、同じく住吉村在住の財界人で創立委員の一人でもあった安宅商会社長・安宅彌吉が女子教育の必要性を訴え、女学校の設立を主唱。 当時住吉村に在住した関西財界人たちの手で創立された「財団法人甲南学園私立甲南中学校」の創立委員会席上において、同じく住吉村在住の財界人で創立委員の一人でもあった安宅商会社長・安宅彌吉が女子教育の必要性を訴え、女学校の設立を主唱。 |
|---|---|
| 1920年(大正09年) |
 「官立にはない自由な校風の私立の女学校」をめざし、甲南高等女学校を設立。校長人事に手が回らず、
初代校長には甲南中学校長の小森慶助が兼任。
校舎もまだ無く、甲南幼稚園の2教室を借用して開校。
「官立にはない自由な校風の私立の女学校」をめざし、甲南高等女学校を設立。校長人事に手が回らず、
初代校長には甲南中学校長の小森慶助が兼任。
校舎もまだ無く、甲南幼稚園の2教室を借用して開校。 |
| 1921年(大正10年) |  「財団法人甲南学園甲南高等女学校」設立認可 「財団法人甲南学園甲南高等女学校」設立認可 初代理事長は住吉村の年長者であり、甲南中学校、甲南小学校・幼稚園の理事長でもある田辺貞吉が就任。創立者・安宅彌吉は会計係を担当。 |
 11月27日、本山村字田中に校舎本館落成。同日を創立記念日とするのはこれが由縁。 11月27日、本山村字田中に校舎本館落成。同日を創立記念日とするのはこれが由縁。 |
|
| 1923年(大正12年) |  小森慶助の辞任に伴い「専任校長が見つかるまで」との約束で第2代校長に三田中学校長・今西嘉蔵が兼任で就任。 小森慶助の辞任に伴い「専任校長が見つかるまで」との約束で第2代校長に三田中学校長・今西嘉蔵が兼任で就任。 |
  第3代にして初代専任校長となる表甚六が就任。以降在任23年、学園の教育精神の基礎を築いていく。 第3代にして初代専任校長となる表甚六が就任。以降在任23年、学園の教育精神の基礎を築いていく。 |
|
| 1924年(大正13年) | 校訓「清く 正しく 優しく 強く」制定  校章を象徴化 校章を象徴化 |
| 1925年(大正14年) | 校友会発足(のちの和光会) 校友会誌『和光』創刊 校友会誌『和光』創刊 |
| 1926年(大正15年) | 田辺貞吉が死去。安宅彌吉が第2代理事長に就任、会計係を兼ね、以降20年に渡って学園を支える。 |
| 同窓会を組織(のちの清友会) 会誌『清友』創刊 |
|
| 1927年(昭和02年) |  新学習法「自学創造教育」を開始。 新学習法「自学創造教育」を開始。 |
| 校歌制定。 第一校歌の一番の歌詞は明治天皇御製一首「まこと」 |
|
| 1929年(昭和04年) |  校旗制定。この際の校旗は同窓会からの寄贈。 校旗制定。この際の校旗は同窓会からの寄贈。 |
| 1930年(昭和05年) | 創立10周年記念式挙行 |
| 1937年(昭和12年) | 後援会を発足 |
| 1938年(昭和13年) |  阪神大水害により校舎埋没。 阪神大水害により校舎埋没。奇跡的に被害者はいなかった。 |
| 1942年(昭和17年) | 旧制専攻科設置、発足。家事科・裁縫科を重点に、修身・国語・家政・理科・法制経済・商業簿記の7科目のカリキュラムを持つ。 修業年限2年。 |
| 1944年(昭和19年) | 都市疎開始まる。学徒勤労令公布。動員につぐ動員で、専攻科で退学者続出。表校長も「生徒の品位が日に日に下落して行く」と憂いた。在校生が別々の場所で勤労奉仕する心細さを憂い、学校工場化を決定。 |
| 1945年(昭和20年) | 6月5日 神戸大空襲により全校舎焼失。 |
| 9月 芦屋の仏教会館1階ホールを借り授業再開。月〜金で毎日一学年ずつ授業し、土曜は焼け跡整理。その後打出の公会堂2階の講堂も借用。 | |
表の後任に、広島高等師範学校第一回卒業生で表と同期の、兵庫県立神戸第1中学校長・池田多助が就任。焼け跡に立って「学校は焼けたが甲南精神は焼けていない」と就任挨拶。 |
|
| 1946年(昭和21年) |  第3代理事長に坂田幹太就任 第3代理事長に坂田幹太就任 |
 同窓会主催で第1回バザー開催 同窓会主催で第1回バザー開催 |
|
| 1947年(昭和22年) |  代表理事に上田要就任 代表理事に上田要就任甲南女子中学校併設認可 |
| 1948年(昭和23年) | 新制甲南女子高等学校設立認可 財団名を「財団法人甲南女子学園」に変更 |
| 1949年(昭和24年) |  第4代理事長に阿部孝次郎就任 第4代理事長に阿部孝次郎就任 |
| 1950年(昭和25年) | 新制専攻科(家政科・英文科)を開設 |
| 1951年(昭和26年) | 昭和22年の学校教育法及び昭和24年の私立学校法の定めにより財団法人から学校法人に切り換え。法人名を「学校法人甲南女子学園」に変更。 |
| 生徒による短大設置の署名活動が始まる。 | |
| 1954年(昭和29年) |  「甲南精神」を知らせるため、創立30周年誌から抜粋し、一部原稿を追加して『甲南の道』(後の学生要覧)を刊行。 「甲南精神」を知らせるため、創立30周年誌から抜粋し、一部原稿を追加して『甲南の道』(後の学生要覧)を刊行。 |
| 新制専攻科廃止 | |
| 1955年(昭和30年) |  甲南女子短期大学開学。家政科を開設(定員40名) 甲南女子短期大学開学。家政科を開設(定員40名)初代学長・池田多助は「中学・高校で甲南常識を、短大で甲南良識を」と考えていた。 学生自治会「清光会」発足 |
| 1956年(昭和31年) | 短期大学に国語科を開設 |
| 1958年(昭和33年) |  第5代校長・短期大学第2代学長に山本栄喜就任。学園の教育精神を「まことの人間をつくる」ということばにまとめ、「聖座」や「ハイ」の実行に哲学的意義を付与した。 第5代校長・短期大学第2代学長に山本栄喜就任。学園の教育精神を「まことの人間をつくる」ということばにまとめ、「聖座」や「ハイ」の実行に哲学的意義を付与した。 |
| 1961年(昭和36年) | 理事会にて創立40周年記念事業として、学園拡充計画を決定。内容は敷地買収と短大学舎新築及び中学校・高校学舎改築。 |
| 育友会会長らが4年制大学設置を理事長・学長に強く要望。学園拡充計画は大学建設と新学舎建設の第2次計画に移行。 | |
| 1964年(昭和39年) | 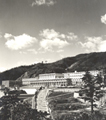 本山町森字坂下町14(現所在地)に甲南女子大学開学。 本山町森字坂下町14(現所在地)に甲南女子大学開学。文学部に国文学科と英文学科を設置(定員各100名)。 初代学長は短期大学長である山本栄喜が兼任。 |
| 短期大学は現所在地の新学舎に移転。この地を清心台と称す。 | |
| 1966年(昭和41年) |  第1回シェイクスピア祭(英文学科)を開催 第1回シェイクスピア祭(英文学科)を開催 |
| 1968年(昭和43年) |  中学校・高校、本山町森字山田4(現所在地)の新校舎に移転。その地を和光台と称す。 中学校・高校、本山町森字山田4(現所在地)の新校舎に移転。その地を和光台と称す。 |
| 1972年(昭和47年) |  第2代学長・第3代短期大学長に鰺坂二夫就任 第2代学長・第3代短期大学長に鰺坂二夫就任 |
| 1974年(昭和49年) | 短期大学を短期大学部に改称 短期大学部に英語科を開設 大学が神戸市建築文化賞を受賞 |
| 1975年(昭和50年) | 大学院文学研究科(修士課程)を開設 文学部に人間関係学科(心理学専攻、社会学専攻、教育学専攻)を開設 |
| 1977年(昭和52年) | 大学院文学研究科博士後期課程を開設 |
| 1978年(昭和53年) |  第5代理事長に芦原義重就任 第5代理事長に芦原義重就任 |
| 文学部にフランス文学科を開設 | |
| 1981年(昭和56年) | 三笠宮殿下、妃殿下ご来臨 |
| 1982年(昭和57年) | 大学で第1回ホームカミングデーを開催 |
| 1984年(昭和59年) | 短期大学部家政科に食物栄養専攻及び生活科学専攻を開設 |
| 1985年(昭和60年) |  皇太子殿下、皇太子妃殿下(現上皇陛下、上皇后陛下)行啓 皇太子殿下、皇太子妃殿下(現上皇陛下、上皇后陛下)行啓 |
| 1987年(昭和62年) | 英文名称をCollegeからUniversityに変更 |
| 1990年(平成02年) |  芦原講堂が神戸市建築賞を受賞 芦原講堂が神戸市建築賞を受賞 |
| 1993年(平成05年) |  第3代学長・短期大学第4代学長に宮城宏就任 第3代学長・短期大学第4代学長に宮城宏就任 |
| 1994年(平成06年) |  第6代理事長に前田義里就任 第6代理事長に前田義里就任 |
| 1995年(平成07年) |  阪神・淡路大震災により
学生の尊い命も犠牲となる。 阪神・淡路大震災により
学生の尊い命も犠牲となる。校舎も一部損壊。 |
| 1996年(平成08年) | 甲南女子大学生協が開業 |
| 1998年(平成10年) | 国際子ども学研究センターを開設 |
| 1999年(平成11年) |  第4代学長・短期大学第5代学長に塩原勉就任 第4代学長・短期大学第5代学長に塩原勉就任 |
| 2001年(平成13年) |  第7代理事長に松下正幸就任 第7代理事長に松下正幸就任 |
| 文学部に多文化共生学科を開設 文学部学科名称を変更 国文学科→日本語日本文学科、英文学科→英語英米文学科、フランス文学科→フランス語フランス文学科 人間科学部(心理学科、人間教育学科、行動社会学科、人間環境学科)を開設 |
|
| 2002年(平成14年) | 心理相談研究センターを開設 甲南女子大学短期大学部を廃止 |
| 2003年(平成15年) | 大学院文学研究科を人文科学総合研究科に名称変更 |
| 2004年(平成16年) | 資格サポートセンターを開設 |
| 2005年(平成17年) |  第5代学長に坪内良博就任 第5代学長に坪内良博就任 |
| 2006年(平成18年) | 文学部にメディア表現学科を開設 人間科学部に総合子ども学科を開設 |
| 2007年(平成19年) | 看護リハビリテーション学部(看護学科、理学療法学科)を開設 |
| 2008年(平成20年) | 学科名称を変更 日本語日本文学科→日本語日本文化学科、多文化共生学科→多文化コミュニケーション学科、行動社会学科→文化社会学科、人間環境学科→生活環境学科 |
| 2009年(平成21年) |  甲南保育園(現在の甲南こども園)を開設 甲南保育園(現在の甲南こども園)を開設対外協力センターを開設 大学図書館において『源氏物語』の最古級写本「梅枝」発見 |
| 2010年(平成22年) | 大学図書館において『古今和歌集』の最古級完本写本発見 |
| 2011年(平成23年) |  第6代学長に松林靖明就任 第6代学長に松林靖明就任 |
| 2012年(平成24年) | 大学院看護学研究科を開設 学科名称を変更 英語英米文学科→英語文化学科 |
| 2014年(平成26年) |  第8代理事長に中内仁就任 第8代理事長に中内仁就任 |
| 2016年(平成28年) |  第7代学長に森田勝昭就任 第7代学長に森田勝昭就任 |
| 2018年(平成30年) | 大学院看護学研究科博士後期課程を開設 医療栄養学部医療栄養学科を開設 |
| 2020年(令和2年) | 国際学部(国際英語学科、多文化コミュニケーション学科)を開設 |
| 2022年(令和4年) |  第8代学長に秋元典子就任 第8代学長に秋元典子就任 |
| 2023年(令和5年) |  第9代理事長に杉⼭健博就任 第9代理事長に杉⼭健博就任 |
| 2025年(令和7年) | 心理学部(心理学科)を開設 |